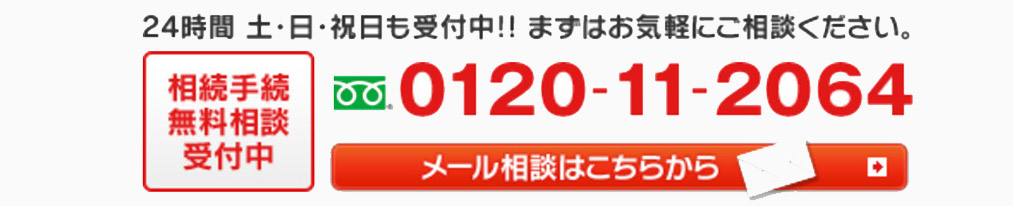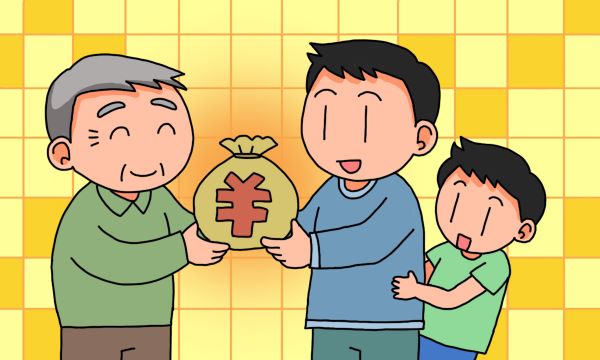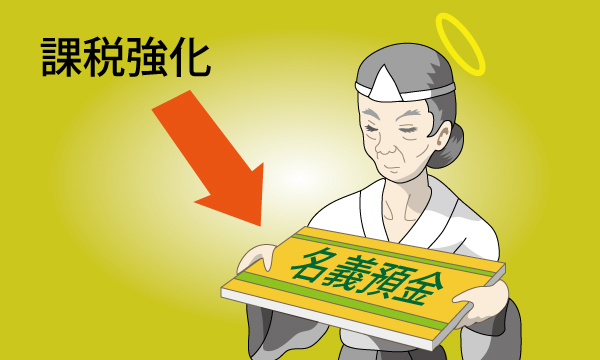民法第900条には、法定相続分が定められています。
1.【配偶者と子】それぞれ2分の1
2.【配偶者と直系尊属(父母など) 】配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
3.【配偶者と兄弟姉妹】配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
4.【同順位の相続人が複数いる場合】原則として人数で等分。
ただし、異母・異父の兄弟姉妹は、同じ両親の兄弟姉妹の相続分の2分の1
2023年(令和5年)4月1日の民法改正により、被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、原則として、特別受益(生前の贈与など)や寄与分(介護など故人への貢献)を考慮せず、この法定相続分によって画一的に行うことになりました(民法第904条の3)。法定相続分は、あくまで遺産分割協議がまとまらない場合の目安となる割合です。
しかし、「法定相続分は当然に受け取れる権利だ!」と思っている相続人は少なくありません。いわゆる「争族」は、この法定相続分がそれぞれの相続人の「実感」と異なるために起きるといっても過言ではないでしょう。
民法第906条には、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と明記されています。この「一切の事情」を考慮して話し合うことは、決して容易なことではありません。
しかし、相続財産は故人が長年の努力や節約によって築き上げてきたものです。家族の行く末を案じて残していた可能性も高いです。
その大切な財産を分け合う際には、単なる法定相続分だけでなく、故人への感謝の気持ちや、これからの生活に対する配慮が欠かせません。
具体的には、「生前に故人の介護やお世話をしてくれた人への感謝」「お墓や仏壇など、祭祀を承継してくれる人への敬意」「故人が亡くなったことで、今後の生活に困る人がいないかという配慮」などを踏まえたうえで、相互に思いやることが大切です。
法定相続分はあくまでも一つの目安です。それぞれの状況を尊重しながら話し合うことができれば、たとえ遺言書がなくても、円満な相続を実現することができるでしょう。