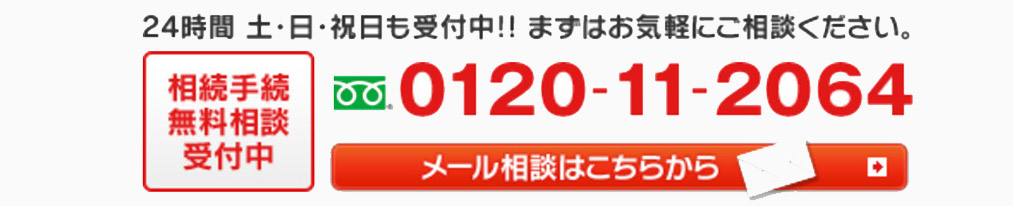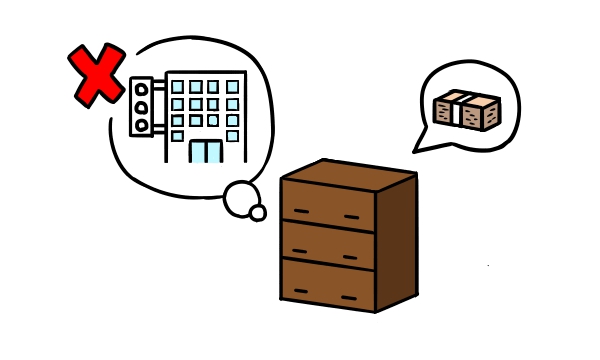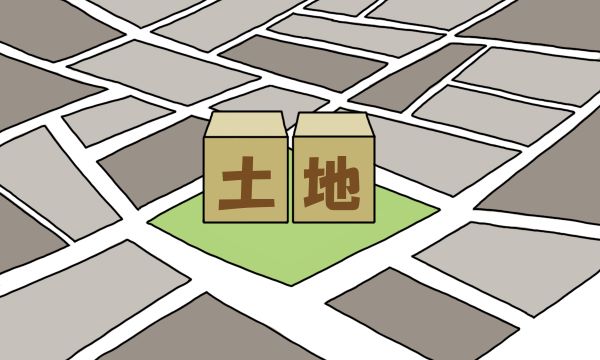一人暮らしの高齢者にとって、ペットはかけがえのない家族です。
心の癒しや孤独感の解消、生活リズムの安定、適度な運動機会の提供、認知機能の維持など、多くのメリットがあります。
その一方で、経済的負担(餌代・トリミング代・医療費など)、飼い主とペット双方の高齢化による世話の負担、旅行や急な入院時の預け先の確保、鳴き声や臭いに伴う近隣トラブル、そしてペットが先に亡くなった後のペットロス症候群といったデメリットも存在します。
また、ご自身が先に亡くなった際のペットの行く末を案じる方も少なくありません。民法上、ペットは「物(動産)」として扱われるため、遺言で直接遺産の受遺者にすることはできません。しかし、ペットの世話をしてくれる人にお金を遺す方法はいくつか存在します。
❶負担付遺贈: 信頼できる人や動物保護団体等に財産を遺贈する際に、「ペットの世話」を条件とします。この場合、遺言執行者を指定しておくと、受遺者がきちんと世話をしているかを確認し、もし怠るようなら家庭裁判所に遺贈の撤回を申し立てることも可能です。ただし、受遺者が遺贈を放棄する可能性があるため、世話を引き受けてくれる人から事前に承諾を得ておくと安心でしょう。
❷負担付死因贈与: 「ペットの飼育を条件に、死亡後、遺産の全部または一部を贈与する」という契約を結ぶことができます。契約なので、①よりも法的拘束力が強いですが、①も②も相続人から遺留分侵害額請求の行使を受ける可能性があります。また、新しい飼い主が適切に飼育をしているか、受け取った遺産をどのように使っているかを継続的に監視することは難しいのが課題です。
❸民事信託(ペット信託): 信頼できる個人または団体にペットの飼育を託し、飼育費を相続財産とは別の「信託財産」として残すことができます。信託契約の内容に基づき、適正にペットが飼育されているかを監督する信託監督人を設定することも可能です。ただし、 契約締結時の初期費用やペットの飼育費用としてまとまったお金が必要なため、高額になりやすく、信託監督人を指定すれば月々の報酬が必要となります。
ご自身の希望や状況、ペットの種類や年齢、受遺者に対する信頼度合など、総合的に考慮し、最も適した方法を選ぶことが重要です。