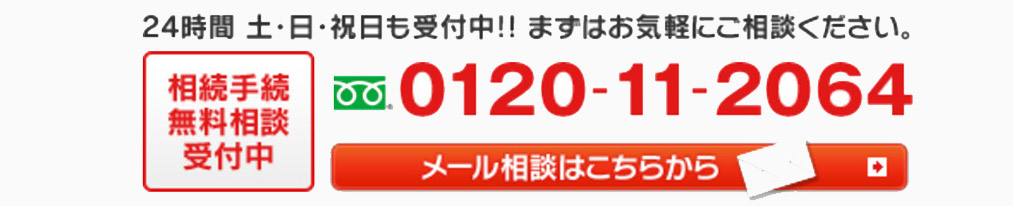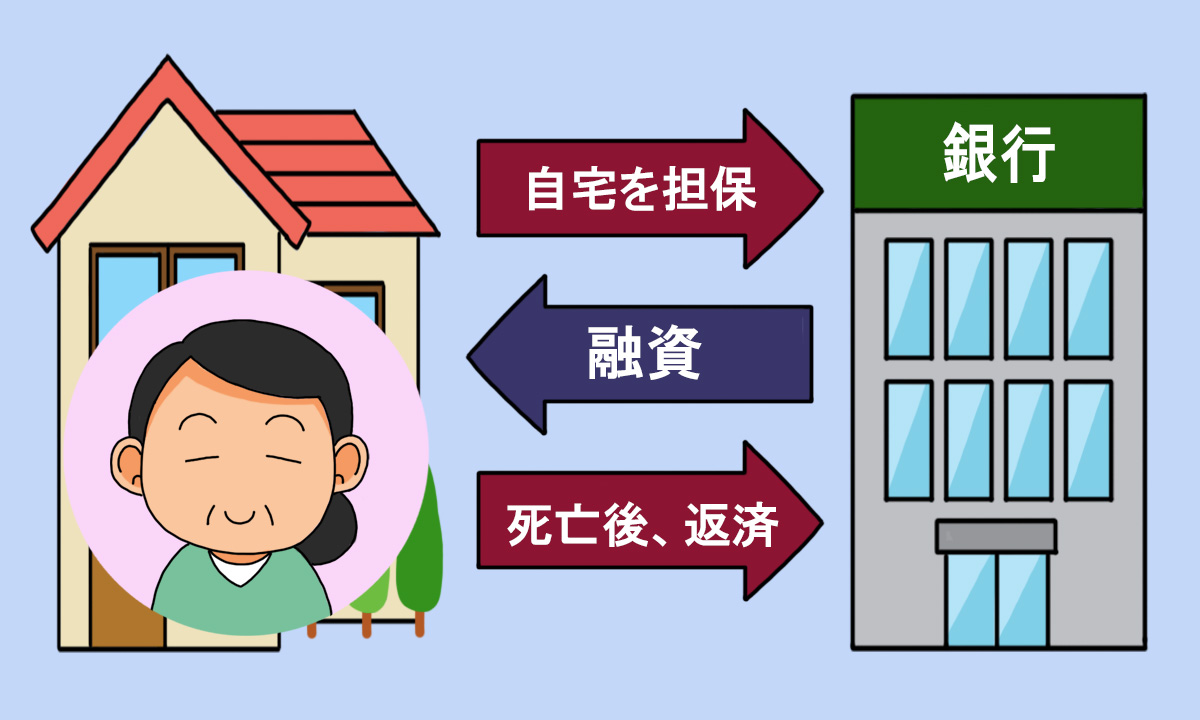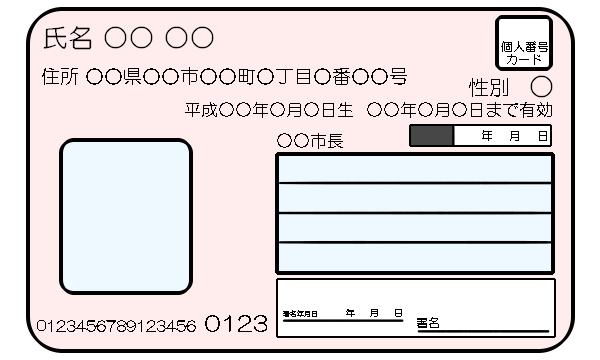遺産分割協議書を作成する際に「お墓や仏壇(祭祀承継)のことも盛り込んでください」というご依頼をいただくことがあります。これには2つの理由があるようです。
後継者不在の課題:「子どもたちが皆、遠くに住んでいるので、誰が故郷のお墓を守るのかハッキリさせたい」
祭祀にかかる負担:「お墓を守っていくのも親戚付き合いをするのも出費を伴うので、財産の中からその負担分を多く相続したい」
神棚や仏壇、お墓、位牌、家系図などの「祭祀財産」は、預貯金や不動産といった一般的な相続財産に算入されないため、遺産分割協議の対象にはなりません。そのため、相続放棄をしても、祭祀財産を引き継ぐことは可能です。これは、祭祀承継は遺産相続とは別物で、故人の意思や昔からの慣習が尊重されるものだからです(民法897条)。
誰がお墓や仏壇を守っていくかがハッキリしていない場合、争族の火種となるリスクがあります。これを避けるためにも、遺言書の中で祭祀承継者を指定しておくことをお勧めします。
遺言書の「遺言事項」の欄に、「〇〇を祭祀主宰者に指定する」と明確に記載することで、指定された人が祭祀財産を法的に引き継ぐことになります。
実際問題として、祭祀承継には出費が伴うため、その費用を考慮し、祭祀承継者の財産取り分を多くする旨を遺言書に明記しておくと、後々の紛争を未然に防ぐことができるでしょう。エンディングノートへの記載は法的効力がありませんが、故人の気持ちを伝える手段としては有効です。
少子高齢化が進む現在において、祭祀承継の問題はますます増えていくでしょう。単に財産を相続するだけでなく、故人やご先祖様が大切にしてきた想いや、代々受け継がれてきたものを引き継いでいく気持ち。これからの時代は、そんな「敬意と感謝の気持ち」が、ますます大切になりそうですね。