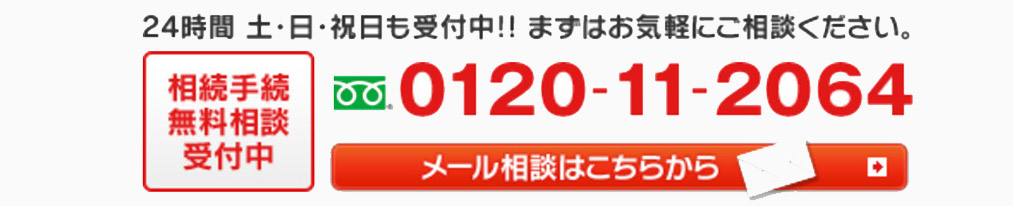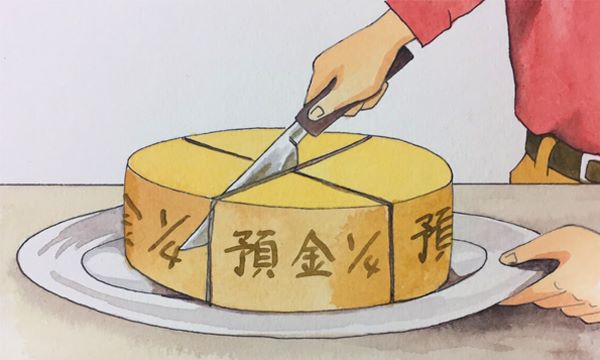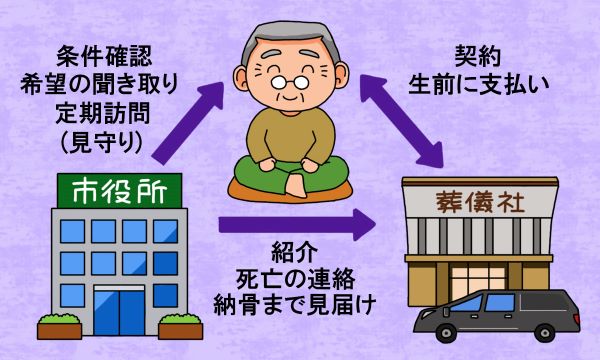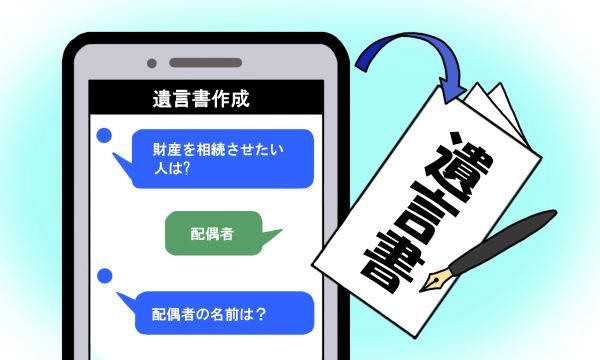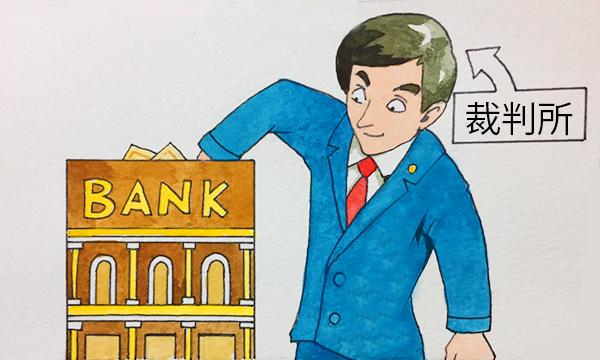総務省の「家計調査」(2024年)によると、高齢無職世帯の毎月の平均支出は、夫婦世帯で約28.7万円、単身者で約16.1万円です。両世帯とも毎月平均3万円前後の赤字が生じており、その不足分は貯蓄を取り崩して補っているのが現状です。
2025年度の老齢基礎年金は満額でも月6.9万円のため、老齢厚生年金を受給していない方は、さらに大きな赤字になることが予想されます。
現在、生活保護受給者の半数以上(52.6%)を65歳以上の高齢者が占めています。就職氷河期世代が65歳になる2035年頃には、低年金が原因で生活保護を受ける高齢者が、さらに増えていくと考えられています。
こうした状況を踏まえ、今回は生活保護を受けている方からよくいただく相続や相続放棄に関するご質問をQ&A形式でまとめました。
<生活保護受給者の相続に関する疑問>
Q1.生活保護を受けていても、遺産を相続できますか?
A.はい、相続できます。ただし、相続した財産の内容・金額によっては、生活保護の受給資格を満たさなくなり、生活保護の減額・停止・廃止になる可能性があります。
Q2.生活保護を打ち切られたくない場合、相続放棄はできますか?
A.生活保護制度は、最低限度の生活を保障するためのものです。そのため、原則として、生活保護受給者が相続放棄することは制限されています。
ただし、相続をすることで生活状況が悪化する可能性がある場合(多額の負債がある場合や、山林・田畑など処分が難しい不動産がある場合など)は相続放棄が認められることもあります。
Q3.生活保護を打ち切られたくないので、相続したことを隠していたらどうなりますか?
A.不正受給が発覚すると、保護費相当額に最大40%を上乗せして徴収される可能性があります(生活保護法第78条) 。
相続する場合も、相続放棄をする場合も、必ず福祉事務所の担当者に事前に相談することをお勧めします。