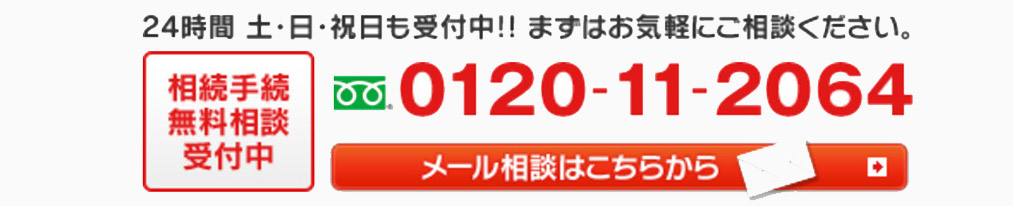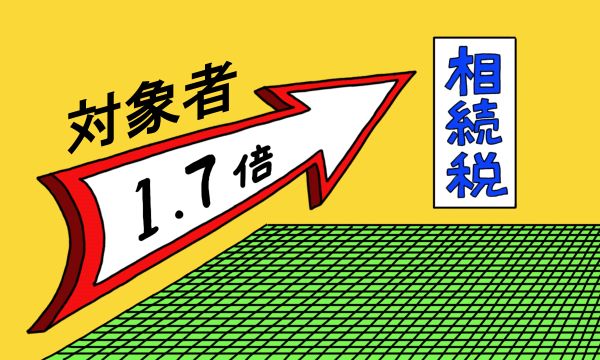Gさんには2人の息子さんがいます。20年以上前に口論の末に飛び出したきり音沙汰のない長男と、Gさんと同居している病弱な二男と。
そこで、Gさんは考えました。「もしも自分が亡くなったら、二男は長男を探し出して遺産分割協議をしなければならない。この家は3000万円の価値があるが、預金は1000万円ほどしかない。長男が法定相続分である2分の1を要求してきたら、この自宅を売却しなければお金を用意できない。そうすると、二男は住む場所に困ってしまう。そうだ。『全ての財産を二男に相続させる』と書いた遺言を作成しよう。ただし、長男が遺留分(相続財産の4分の1)を要求してくる可能性がある。それならば、契約者・被保険者が私、受取人が長男という内容の生命保険(1000万円)に入っておこう。長男が遺留分を請求して来たら、二男から長男にこの保険金を遺留分として受け取るように伝えてもらえばいい・・・」
Gさん、ちょっと待った!
生命保険金は受取人固有の財産という考え方のため、遺産分割の対象になりません。したがって、長男は保険金の受取りとは別に、遺留分を請求することができるため、請求された場合、二男は遺留分を捻出するために自宅を売らなければならないかもしれません。
では、どのように対策をすればいいのでしょう。
この場合、契約者・被保険者がGさん、受取人が二男という内容の生命保険(1000万円)に入ることをおススメします。そうすると、長男が遺留分を請求した時に二男は保険金から支払うことができます。また、長男が遺留分の侵害を「知った時」から1年以内、または相続の開始から10年以内に遺留分を請求してこなければ、その保険金は二男が自由に使うことができます。
遺留分確保のために生命保険を利用する場合は、受取人を間違えないように気を付けましょう。