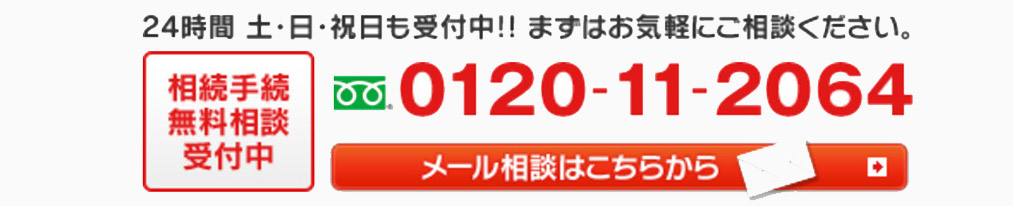「相続税なんて、お金持ちだけの話でしょ?」 多くの方がそう思っているかもしれません。
しかし、その認識はもはや過去のものです。
国税庁のデータによると、2023年にお亡くなりになった方のうち、相続税の課税対象となったのは9.9%。
これは、およそ10人に1人が相続税を申告している計算になります。
良かれと思って進めた相続対策が、複雑な税金のルールや近年の制度改正によって、かえって多額の税金を生んでしまうケースも少なくありません。
この記事では、意外と知られていないけれど影響の大きい「5つの落とし穴」を、具体的な事例とともに解説します。
1. 「良かれと思った」養子縁組で、税金が激増する
歯科医のAさんは、ご自身の死後、遺産分割で親族が揉めることを避けるため、弟のBさんを養子に迎え、唯一の相続人としました。これで一安心、と思いきや、これが大きな間違いでした。
養子縁組をしなければ、相続人は弟妹とその子供たち(代襲相続人)の合計7人。
この場合の相続税の基礎控除額は7,200万円でした。しかし、養子縁組によって相続人がBさん1人になったことで、基礎控除額は3,600万円に半減。結果として、Aさんの遺産には多額の相続税が課されることになってしまったのです。
この事例が示すのは、家族関係を円満にしようという善意の行動が、税務上は全く逆の結果を招く可能性があるという厳しい現実です。事前に専門家へ相談していれば、遺言書を作成することで、税金の負担を増やすことなく争いを避けることも可能でした。
この件に限らず、税務の専門家は次のように警鐘を鳴らしています。
安易な節税対策を行うと、必ず手痛いしっぺ返しがくるという、典型的な事例です。
2. 海外資産はもう隠せない。国税庁は「数百万件の口座」を把握済み
「資産を海外に移せば税務署には分からない」――そんな時代は、完全な終わりを告げました。
その背景にあるのが、CRS(共通報告基準)という国際的な制度です。これにより、世界各国の税務当局が金融口座の情報を自動的に交換するようになりました。日本がこの制度に参加した2018年、国税庁は約55万件もの日本居住者の海外口座情報を入手しましたが、驚くべきはその翌年です。
2019年には、その数が約189万件へと爆発的に増加しました。これに対し、2016年に自主的に提出された「国外財産調書」はわずか9,102件。この数字を比較すれば、どれほど巨大な情報網が完成したかは一目瞭然です。
国税庁にとって、このデータは税務調査を進めるための「宝の山」です。
グローバルな情報共有が進む今、資産の透明性を確保することだけが唯一の正しい戦略と言えるでしょう。
ついに、資産を海外で隠すことが不可能になりましたね。
3. 節税の王道「タワマン節税」は最高裁に封じられた
かつて節税の王道とされたのが「タワマン節税」です。これは、タワーマンションの市場での売買価格(実勢価格)と、相続税を計算する際の評価額との間に大きな差があることを利用して、相続財産を圧縮する手法でした。
しかし、この手法に大きな転機が訪れます。ある相続で、約13億8700万円で購入された2棟のタワーマンションを、相続人たちは相続税の路線価評価に基づきわずか約3億3000万円と評価して申告しました。
これに対し国税庁は、「著しく不適当」として財産評価基本通達の総則6項、通称「伝家の宝刀」を発動。不動産鑑定により評価額を約12億7300万円と再計算し、約3億3000万円もの追徴課税を行ったのです。この処分を不服とした相続人との争いは最高裁まで持ち込まれましたが、最終的に国税庁の主張が認められました。
この判決をきっかけに、2024年からはルールが正式に改正され、マンションの相続税評価額は市場価格の最低でも6割程度まで引き上げられることになりました。
これにより、タワマン節税という人気のあった節税の抜け道は、事実上、封じられたのです。
4. 「あげたつもりない」が一番危ない。「みなし贈与」の罠
贈与というと「あげます」「もらいます」という正式な合意があるものと考えがちです。しかし、税務署は当事者の意図とは関係なく、お金の流れの実態を見て「これは実質的な贈与だ」と判断することがあります。これが「みなし贈与」です。
この「みなし贈与」は、悪意のない日常的な行為の中に潜んでいるため、特に注意が必要です。
* 夫婦間の住宅ローン返済: 夫名義の住宅ローンを、妻が自身の預金から返済した場合、その返済額は妻から夫への贈与とみなされる可能性があります。
* 保険契約の名義変更: 父親が保険料を支払ってきた生命保険の契約者を、途中で子供に変更した場合、その時点での解約返戻金相当額が、父親から子供への贈与とみなされることがあります。
* 著しく低い価格での売買 (低額譲渡): 親族間で不動産などを市場価格より著しく低い金額で売買すると、市場価格との差額分が贈与とみなされ、贈与税の対象となる場合があります。
これらのケースは、税金逃れではなく家族を助けたいという善意から行われることがほとんどです。しかし、税務署に対して「知らなかった」は通用しません。
5. 「暦年贈与」はルール変更。これからは「相続時精算課税」が新常識?
生前贈与の基本であった「暦年贈与」に大きなルール変更がありました。
これまでは亡くなる前3年以内の贈与が相続財産に加算(持ち戻し)されていましたが、2024年1月1日以降の贈与からは、この期間が7年まで延長されます。
この延長は段階的に適用され、2027年以降に発生する相続から持ち戻し期間が徐々に長くなり、2031年1月1日以降の相続で完全に7年間となります。(なお、延長された4年間の贈与額からは合計100万円の控除が可能です。)
一方で、これまで使い勝手が悪いと敬遠されがちだった「相続時精算課税制度」が、驚くほど使いやすく改良されました。最大の変更点は、年間110万円の新たな基礎控除が創設されたことです。
この110万円までの贈与は、贈与税の申告が不要なうえ、相続時の持ち戻しの対象にもなりません。
この改正は、相続対策の戦略を根本から見直す大きな転換点です。申告不要で持ち戻しの対象にもならないこの新しい年間110万円の非課税枠は、事実上、従来の暦年贈与に代わる優れた選択肢となります。
特に直系尊属から子や孫への資産移転において、この枠内の贈与であれば、7年間の持ち戻しリスクを完全に排除できるため、より安全で計画的な生前贈与が可能になったのです。
まとめ
相続税や贈与税のルールは非常に複雑なだけでなく、毎年のように改正が加えられています。そして税務署は、AIやビッグデータを活用し、これまで以上に個人の資産状況を正確に把握するようになっています。
安易な知識や古い情報に基づく対策は、かえって家族を大きなリスクに晒しかねません。
あなたの相続対策、本当に最新のルールでチェックできていますか?専門家への相談が、将来の家族を大きなトラブルから守る第一歩かもしれません。