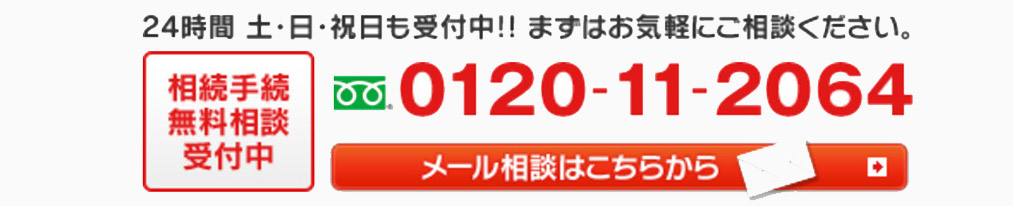70歳で歯科医のAさんが死亡しました。
Aさんは独身で子どももいません。死亡直前まで現役でバリバリお仕事をされており、身の回りのことやお金の管理も自分でされていました。Aさんは癌で、余命を悟り、自分の死後のことを考えておられました。
推定相続人となるのは、弟Bさん・弟Cさん・妹Dさん・既に死亡した妹Eさんの子4名(代襲相続人)の7名でしたが、甥姪(妹Eの子)とは折り合いが悪く、遺産分割で揉めることが予想されました。
Aさんと兄妹は、遺産分割で揉めることは嫌だと考え、BさんがAさんの養子になることを決め、養子縁組の手続を行いました。これで、もう遺産分割で揉めることはない。程なくして、Aさんは死亡し、相続の手続を行うことになりました。
Aさんは歯科医でしたから、それなりの財産がありました。その額はBさんの予想をはるかに超えていました。
養子になったBさんは唯一の相続人ですから、遺産分割で揉めることはもちろんありませんでした。しかし、養子縁組をしたことで税金の負担が増えることになりました。
養子縁組をしていなければ1億2千万円だった基礎控除額が、養子縁組をしたことで6,000万円になり、それに伴い多額の税金を支払うことになったのです。
相続開始前に相談を受けていたら、相続対策として遺言作成を検討することもできましたが(他の兄妹らには遺留分はありませんから、Aさん1人がすることができます。)、相続開始後では後の祭りです。
相続対策では、様々な角度からの検討が必要なのです。