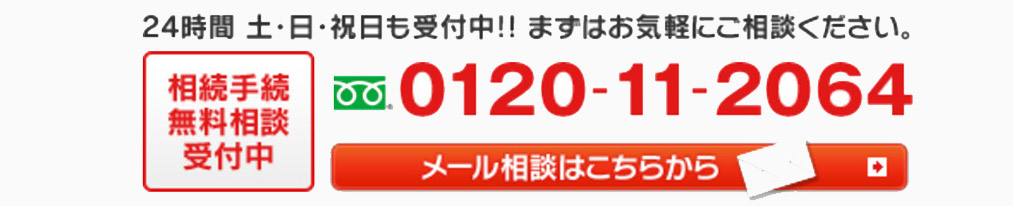遺言や相続は、誰もがいずれ直面する可能性のある、非常に身近なテーマです。しかし、「うちは家族仲が良いから大丈夫」「財産なんて大してないから関係ない」と思い込み、その準備を後回しにしていないでしょうか。
相続の現場で数多くのご家族を見てきた経験から、最も避けたいのは「知らなかった」ことが原因で起こる争いです。実は、相続をめぐる法律はここ数年で大きく変化しており、私たちが「常識」だと思っている知識が、もはや通用しないケースが増えています。法改正や、一般にはあまり知られていないルールを知らないまま自己判断で準備を進めると、思わぬトラブルや不利益を招きかねません。
この記事では、相続実務の専門家として、多くの方がご存じない、あるいは誤解しがちな遺言と相続の「新常識」を5つ厳選して解説します。あなたの知識は本当に最新ですか?ぜひ、ご自身の備えを見直すきっかけにしてください。
1. 「え、遺言書でできるの?」生命保険の受取人は変更可能。でも…
「生命保険の受取人を、遺言で変更することはできますか?」 実務の現場で、時折このようなご相談を受けます。多くの方が、保険の手続きは保険会社でしかできないと考えていますが、結論から申し上げますと、遺言による生命保険金受取人の変更は「認められます」。
これは、平成22年(2010年)に施行された保険法第44条で明確に定められています。遺言でできること(遺言事項)は法律で決められており、その中には財産処分に関する事項として、生命保険の受取人変更も含まれているのです。
ただし、この方法には実務上、大きな落とし穴があります。遺言書に受取人変更の記載があっても、相続発生後に元の受取人が先に保険会社へ請求し、支払いを受けてしまえば、その保険金を取り戻すのは極めて困難です。
確実にご自身の意思を反映させるためには、やはり生前に保険会社へ連絡し、所定の書類で受取人変更の手続きを済ませておくのが最も安全な方法と言えるでしょう。
2. 事業承継の救世主?「財産」ではなく「お金」で解決する遺留分制度
特に中小企業の経営者にとって、事業承継は相続における最大の課題の一つです。近年の法改正で、この課題に対応するための重要な変更がありました。それが「遺留分」制度の見直しです。
問題提起:改正前のリスク 例えば、会社の経営者である父親が「事業に必要な会社の不動産(評価額1億円)を、後継者である長男に相続させる」という遺言を残したとします。この場合、他の相続人である二男にも「遺留分」(このケースでは遺産の4分の1=2500万円)を請求する権利があります。
改正前の制度では、長男に2500万円の現金がなければ、不動産を二男との共有名義にするか、最悪の場合は売却して現金を作らなければならず、「事業が続けられなくなる」という深刻なリスクがありました。
解決策(新制度):金銭での支払いが原則に この問題を解決するため、改正後の法律では、遺留分は原則として「金銭で支払う」ことになりました。
これにより、長男は事業用資産である不動産そのものを守りながら、二男に対しては金銭でその権利を保障することができます。すぐに現金が用意できない場合でも、裁判所の許可を得て支払いを猶予してもらったり、分割払いにしたりすることも可能です。この改正は、まさに「事業が円滑に継承できるように」という目的を反映したものなのです。
3. 親切が仇に?お世話になった人への遺贈に潜む「税金の罠」
「長年お世話になったお隣りさんに、感謝を込めて自宅を遺したい」「活動を応援しているNPO法人に寄付したい」といった、ご自身の財産を相続人以外の人や団体に残す「遺贈」。この親切な行為には、意外な税金の落とし穴が潜んでいます。
個人への遺贈 相続人ではないお隣りさんが遺贈で不動産を受け取った場合、複数の税金が関係してきます。
*相続税: 遺産総額が基礎控除額を超えている場合、相続人でなくても相続税が課されます。さらに、配偶者や子、親以外の人が財産を受け取ると、相続税額が2割加算されるペナルティがあります。
*不動産取得税: 「特定の不動産を遺贈する」という「特定遺贈」の場合、もらった人が課税対象となります。この税金が課されるのは、特定の資産を贈る「特定遺贈」だからです。もしこれが遺産全体の割合を贈る「包括遺贈」であれば、受遺者は相続人と同様に扱われるため、この税金は課されませんでした。
法人への遺贈 遺贈先が株式会社などの営利法人の場合、受け取った財産は受贈益とみなされ、法人税が課せられます。
相続人への課税という最大の罠 そして、最も注意すべき点が「みなし譲渡所得税」です。例えば、2000万円で購入した不動産が、亡くなった時点で4000万円に値上がりしていたとします。この不動産を法人に遺贈した場合、差額の2000万円(含み益)は「みなし譲渡所得」とされ、所得税が課税されます。
驚くべきことに、この納税義務を負うのは、財産を受け取った法人ではなく、亡くなった方の「相続人」なのです。
事例では、甥がこの税金を支払う義務を負うことになりました。善意の遺贈が、意図せずして相続人に重い税負担を強いる結果になりかねないのです。
4. それ、実は無効です!夫婦の「共同遺言」とよくある勘違い
遺言書に関しては、「こうだろう」という思い込みが法的には全く通用しないことがよくあります。ここでは、特に陥りやすい勘違いをいくつかご紹介します。
共同遺言の禁止 「夫が先に亡くなったら妻に、妻が先に亡くなったら夫に全財産を相続させる」といった内容で、ご夫婦が仲良く連名で1通の遺言書を作成するケースがあります。しかし、これは民法第975条で明確に禁止されている「共同遺言」にあたり、無効となります。遺言は必ず一人ひとり、別々の書面で作成しなければなりません。
遺言の有効性については、様々な俗説がありますが、判例や法律に基づくと意外な事実がわかります。例えば、複数枚にわたる遺言書に契印(割印)がなくても、有効とされた判例があります。
遺言書が数葉にわたるときであっても、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日附、署名、捺印が適法になされている限り、右遺言書を有効と認めて差支えないと解するを相当とする。(最判昭和36年6月22日)
この他にも、
*封印された遺言書を家庭裁判所の検認前に開封してしまっても、遺言書自体が無効になるわけではありません(ただし、5万円以下の過料に処される可能性があります)。
*自筆証書遺言の押印は、実印でなく認印や拇印でも有効です。
これらの「常識」を鵜呑みにせず、法的に正しい形式で作成することが何よりも重要です。
5. 遺言もデジタル化の時代へ。法務局の保管制度と未来の「デジタル遺言」
紙とハンコの世界というイメージが強い遺言ですが、今、急速にデジタル化の波が押し寄せています。
現在の進化:法務局の保管制度 まず、自筆証書遺言のルールが緩和され、財産目録についてはパソコンでの作成が認められるようになりました。 そして、最も大きな変化が、2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」です。これは、作成した自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度で、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。さらに、この制度を利用した場合、相続発生後の「家庭裁判所での検認」が不要になるという大きなメリットがあります。
未来の展望:デジタル遺言とオンライン化 現在、法制審議会では、さらに進んだ「デジタル遺言書」の導入が検討されています。 この構想では、パソコンやスマートフォンで遺言書を作成し、データとして保管することが可能になります。偽造や改ざんを防ぐため、親族以外の「証人の立ち会い」と、本人が内容を口述する様子の「録画」が要件とされる見込みで、2026年を目処に関連法の改正が目指されています。
さらに、公証人が作成する最も確実な「公正証書遺言」も、オンラインでの作成手続きが2025年度前半の運用開始を目指して準備が進んでいます。遺言の世界は、私たちが思っている以上に、早く、大きく変わろうとしているのです。
まとめ
ここまで見てきたように、遺言と相続の世界は、法改正や新しい制度の導入によって常に変化しています。古い知識や安易な自己判断は、かえって家族を混乱させ、争いを引き起こす原因にもなりかねません。
最も重要なのは、「ご自身の最後の意思を、法的に有効な形で、確実に実現させること」です。そのためには、最新の正しい知識に基づいた準備が不可欠です。
あなたの未来への備えは、変わりゆく時代のルールに対応できていますか?この機会に一度、専門家への相談も含めて、じっくりと検討してみてはいかがでしょうか。