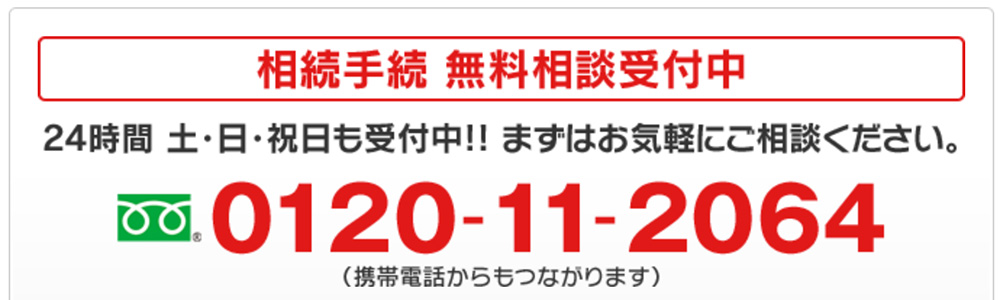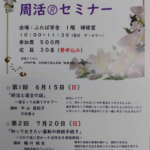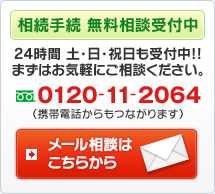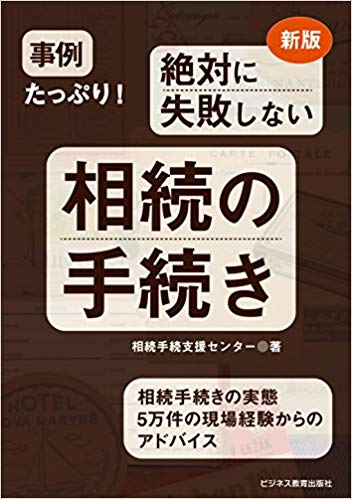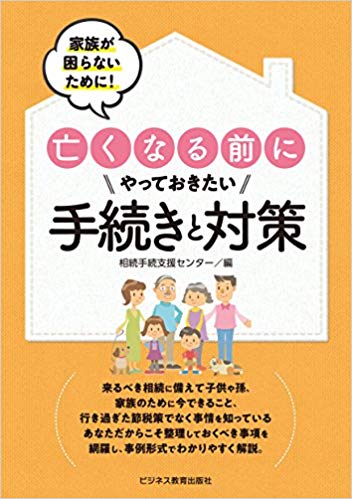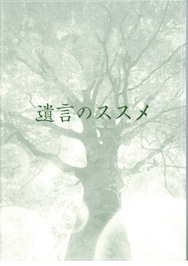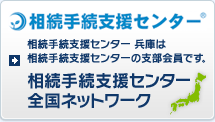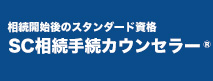質問:弟と亡父の共有名義のマンションがあります。1,500万円は父が出しました。父が亡くなって18年になりますが、名義を変更しないままになっています。このマンションには弟の夫婦が住んでおり、母と私は別の家に住んでいます。このマンションの名義をすべて弟に変更する場合、私と母は、相続分としていくらかを請求することはできますか?
回答:今回の相談は、お父さんと弟さんが半分ずつ資金を出して購入したマンションの共有持分(2分の1)の相続に関するものですね。
このマンションの共有持分2分の1はお父さんの相続財産ですから、遺言がなければ、最終的には共同相続人である配偶者と子2名全員で遺産分割協議をして誰がどれだけ相続するかを決めることになります。
遺産分割協議においては、相続人全員の合意がある限り、内容的にはどのような分割がなされてもよいとされています。したがって、本件のマンションの共有持分を弟さん一人が相続するという内容の協議をすることができます。
しかし、民法には法定相続分が定められていますから(民法900条)、配偶者であるお母さんは2分の1、子である相談者は4分の1の権利をそれぞれ主張することができます。
このマンションの他にも遺産があればそれを分けることもできますが、遺産がこのマンションしかない場合には、それをどうやって公平に分けるのか問題になります。
例えば、弟さんが住んでいるマンションの持分を法定相続分にしたがって複数名で相続することもできますが、このような共有関係は権利関係を複雑化させることになるためおすすめできませんし、今回の相談者もマンションの持分自体を相続するつもりはないようです。また、弟さんが実際に住んでいるため、マンションを売却してその代金を分けるというのも現実的ではありません。
このような場合には、当該マンションは弟一人が相続する代わりに、他の相続人には弟からそれぞれの相続分に応じた代償金を支払う「代償分割」という方法が考えられます。
今回も代償分割という方法の遺産分割協議を検討されてはどうでしょうか。
仮にマンションの持分が1500万円の価値があるとして法定相続分で算定すると、お母さんは750万円、相談者は375万円の代償金を貰えることになります。
ただし、法定相続分という割合はあくまで基本的な目安に過ぎず、相続人の中で被相続人から特別な受益を受けた者がいた場合や(特別受益:民法903条1項)、逆に被相続人の遺産の増加・維持に特別の寄与をした者がいた場合(寄与分:民法904条の2第1項)などは、法定相続分が修正される可能性があります。
また、遺産分割は「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」なされるとされていますから(民法906条)、相続人間でしっかりと話し合ってお互いが納得した上で決めることが大切です。どうしても話し合いがまとまらない場合には、裁判所を利用することになるでしょう。

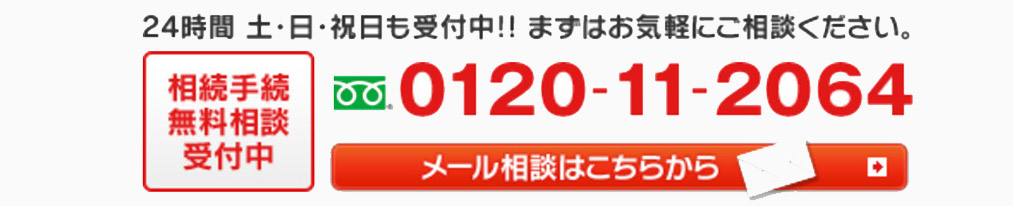
 代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。