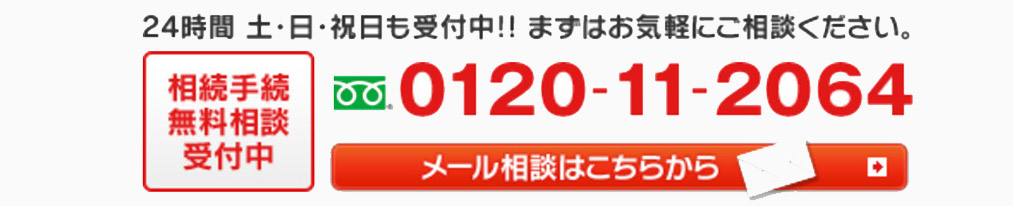最近、遺産分割協議書に祭司承継を盛り込んで欲しい旨の依頼が多くあります。
原因として、
(1)故人の近隣地域に、子世代の誰もが住んでおらず、誰が墓守をするかをはっきりさせたい
(2)田舎において、祭祀の承継者は親類・近所付合いをすることが多く、そのために多くの出費を負担する。その負担分として、相続財産から祭祀の承継費用分として一定額を祭祀承継者は相続したいと考える。
核家族化と移動により、先祖代々の土地に住まないことがお墓をどのように守るか、また、親類や近所付合いの費用をどのように見積もるかが、相続の重要なポイントとなってきています。
最近の事例として
(1)相続人は配偶者(後妻)と先妻の子(長男、長女)
(2)配偶者は故人の墓守を行わない。
(3)配偶者は土地、建物を売却し、他県に移住予定。
(4)誰が墓守をするかが遺産分割協議のポイントとなり、長男が若干多く金融資産を相続し、遺産分割協議はまとまった。
(5)遺産分割協議後、長男は海外に転勤
永代供養をすれば事足りるか・・・これから祭祀承継の文言が死語化する可能性を秘めている事例で、正解がない事例です。